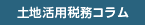コラム vol.500-1
コラム vol.500-1相続・遺産分割の基本(1)不動産オーナーのための遺言書
公開日:2024/04/26
遺言は、15歳以上で、かつこれを十分に理解できる能力(意思能力)を有する人間が行うことができ、自分の死後の財産の帰属等を決めることのできる法律行為です。遺言は、民法の定めた方式に従って行わないと効力が認められません。遺言は遺言者の死亡によってその時から効力が生じます。相手方の承認は不要です。
通常の方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」、「自筆証書(前項の目録を含む)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない」と、民法で定められている遺言の方法です。
自筆証書遺言では、遺言者本人が直筆で①遺言の本文、②日付、③氏名のすべてを手書きし、認め印でもよいので押印をすることが必要です。過去の裁判では、他人が手を添えて運筆を助けたものが無効とされています。なお、自筆証書遺言は法律で要式が決まっていますので、遺言者の意思を伝えるものだとしても紙に書かずに録音や映像を残していても、「遺言」としては認められません。
民法改正により、遺言の本文を手書きすれば、財産目録はパソコン等で作成でき、通帳や登記事項証明書のコピーに番号を付けたものも目録として使用できるなど、大変作成しやすくなりました。一方で、手軽に作成できる分、その作成に第三者が介入しないため、偽造や変造等のリスクも他の形式より高いものといえます。
また、自筆証書遺言のうち一部分を訂正する際には変更箇所に印を押し、変更した内容を明記「第1条1行目1字挿入」等)した上で習名もいるなど、細かな部分まで制約がありますので、作成にあたっては十分な確認が必要です。
自筆証書遺言は原本1通のみが存在する遺言ですから、誤って破棄されたり、その存在を知られていなかったために、いざ相続が発生した時に発見されないといったことのないように、保管方法についても気を配っておきたいものです。この保管の点についても遺言書保管法が新たに立法され、すでに全国の法務局で封をしていない自筆証書遺言の保管制度が開始されており、この制度を利用することにより原本紛失の危険がなくなるほか相続発生後の検認手続も不要となるため安心できるでしょう。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が法律で定められた方式に従って作成する遺言です。作成に当たっては、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口で伝えるなどの要件があるため、自筆証書遺言に比べると必要な事項が多い遺言です。しかし、今では公証人には事前に文章で作成したい遺言の内容を伝えることが大半です。公証人が作成に関与するため、形式的な面で無効となることはほぼない遺言です。
遺言作成の手数料を支払う必要はありますが、出張してもらうことも可能なため、意識ははっきりしているが長文を自身で手書きすることができない人でも利用することができます。
公正証書遺言は検認の手続が不要であり、原本は公証役場で保管されるため紛失のリスクがないという長所があります。また、遺言者の死後には全国の公証役場で検索をかけることができ、発見されやすいこともメリットです。デメリットとしては、遺言をする財産の額によって公証人に支払う手数料が変わるため、資産が多額であると作成費用が高額になります。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な性質を有する遺言といえるでしょう。作成方法は、遺言者が遺言を作成してそれに署名押印を行い、これを封筒に入れて遺言書に押印したのと同じ印鑑を使って封印して、この封筒を公証人と証人2人の前に提出して、公証人に認証してもらいます。費用は1通11,000円と決まっています。
秘密証書遺言は、自筆証書遺言とは異なり、本文を含め署名以外の部分は自身で手書きする必要はありませんから、パソコン等で作成することができるため、手軽でより作成しやすい遺言書といえるでしょう。ただ、公正証書遺言や法務局保管を選択した自筆証書遺言とは異なり、秘密証書遺言の原本は1通しか存在しませんから、破棄や未発見のリスク等がありますので、保管方法等については気を遣う必要があります。
遺言の限界と遺留分
遺言でも侵害することのできない「遺留分」があります。
相続人は遺留分を侵害する遺贈や相続分の指定、生前贈与等に対しては、遺留分侵害額請求を行うことにより、遺留分の限度で代償金等を取得することができます。
民法では相続分の割合を法律で定めていますが、遺言の自由も認め、被相続人が自己の相続開始前に誰にどの財産を相続させるかを自由に決めることも認めています。しかし他方において「一定の相続人のために法律上遺留されるべき相続財産の一定部分」である遺留分を認め、兄弟姉妹以外の法定相続人には最低限の取得分を認めています。
その遺留分の割合は、父母等の直系尊属のみが相続人の場合は相続財産の3分の1、それ以外の場合は2分の1となります。兄弟姉妹やその代襲相続人(甥や姪)には遺留分が存在せず、兄弟姉妹は被相続人の行った生前贈与や遺贈については、遺留分侵害額請求を行うことができません。
表:遺留分割合
| 配偶者の遺留分 | 血族相続人全体の遺留分 | |
|---|---|---|
| ①配偶者のみが相続人である場合 | 1/2 | なし |
| ②子のみが相続人である場合 | なし | 1/2 |
| ③直系尊属のみが相続人である場合 | なし | 1/3 |
| ④兄弟姉妹のみが相続人である場合 | なし | なし |
| ⑤配偶者と子が相続人である場合 | 1/4 | 1/4 |
| ⑥配偶者と直系尊属が相続人である場合 | 1/3 | 1/6 |
| ⑦配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合 | 1/2 | なし |
遺留分を侵害する遺言は作成できるのか
遺留分を侵害するような遺言でも作成することは可能です。遺留分を侵害するような内容の遺言書を作成したとしても、侵害された遺留分権利者から遺留分侵害額請求権を行使されるだけで、遺言自体が無効になることはありません。専門家に相談した際に遺留分を侵さない遺言にすることを勧められるのは、残された相続人等に遺留分侵害額請求をされるという負担を残さず、裁判まで至る可能性を可能な限り低くしておくためです。
ただし、相続人の中に行方不明者がいる場合の遺言や、わざわざ生前に推定相続人に遺留分放棄をしてもらった場合の遺言にまで遺留分を確保する必要はありません。相続人間の関係やこれまでの経緯、多くを遺される相続人が遺留分侵害額請求を受けても構わないと覚悟をしているかという個別の事情を踏まえて遺言の内容を考えることが大切です。
遺留分を侵害する内容の遺言を遺す場合には、多くの財産を取得する相続人が他の相続人に支払う代償財産を用意しておくことが重要です。遺留分侵害額請求を受けた際には、現金として支払うことのできる財産、つまり預貯金等の流動資産が必要になりますので、流動資産として遺産の確保が重要です。単に遺言を遺すだけでなく、生命保検等を活用した代償財産の確保にも気を配り、争いが起こらない相続を実現してください。