自然豊かな伊賀の里山で180余年にわたり
焼き物を生産し続けてきた窯元、長谷園(ながたにえん)。
伊賀焼の文化の継承や故郷への思い、ものづくりに対するこだわりについて
八代目当主の長谷康弘さんにお話を伺いました。
日本唯一を誇る 伊賀の陶土と文化
忍者で有名な三重県伊賀市。四方を山に囲まれた丸柱(まるばしら)地区に、小さな焼き物の産地があります。唯一無二のものづくりを追求する長谷園も、伊賀焼の里をけん引する窯元のひとつです。あるいは長谷園の名前よりも、「かまどさん」と名付けられた土鍋の方が有名かもしれません。画期的な炊飯土鍋としてさまざまなメディアで取り上げられ、長きにわたって愛され続けている看板商品です。
土鍋のご飯が美味しいとは知っていても、火加減が難しく吹きこぼれて後始末が大変というイメージが伴うもの。かまどさんはそんな常識を覆し、手に取った人に驚きと感動を与えます。お米と水を入れて中強火にかけ、穴から蒸気が出たら火を止めてしばらく蒸らすだけ。至って簡単な手順で、至福のご飯がいただけます。
長谷園の土鍋の強みは、原料となる伊賀の土の特徴にあります。大昔には琵琶湖の底だったそうで、ここで採れる陶土には有機物がたくさん含まれています。高温の窯で焼くとそれらが焼失し、気孔のある状態に。そのため、耐熱性や蓄熱性が高まり、調理器具として優秀な働きができるのです。
「日本各地に陶磁器の産地はたくさんありますが、地元産の天然の陶土で土鍋を作れるのは伊賀だけです」と八代目当主の長谷康弘さん。産地としての規模は小さくても、その特徴を最大限に活用するものづくりを誇りに思っておられます。

写真左がかまどさん三合炊き、右が二合炊き
この環境こそが財産に
天保3(1832)年、16連房の登り窯を築き、土鍋や土瓶などを生産したことから長谷園の歴史は始まります。伊賀には良質の陶土に加え、窯の燃料アカマツが用意しやすいという利点がありました。以来200年近くにわたり、時代に求められる製品づくりが続いています。
六代目の時代にはビル外装用のタイル製品がヒット。また、七代目の時代には陶壁画の受注も増えました。バブル期の建設ラッシュも手伝ってタイル事業が拡大し、一時は全売り上げの7割にも及びました。
しかし、1995年、阪神・淡路大震災が大きな転機に。重いタイルを高層階に貼ると地震の揺れが増幅されると報じられたことから、一気に事業は後退しました。運悪く設備投資を行った直後でもあり、これで長谷は終わったと噂されるほど、どん底の状態となりました。
その頃、長谷家の長男康弘さんは東京にいました。小学校まで伊賀で過ごし、実家を離れて市外の中学に通ったのち、高校、大学は東京へ。卒業後は都内の百貨店に勤めていました。長谷園には製造や開発の技術はあるが、世に出す力が足りない。いつか故郷に役立つために流通を学ぼうと考えていました。
震災の2年後、家業を継いだ康弘さん。江戸時代からの伝統を終わらせまいと知恵を絞ったところ、目の前にある山の風景が心に語りかけてきました。鉄道も通っていない、便利とは言い難い場所。しかし豊かな四季の景色があり、ものづくりの文化がある。この環境こそが貴重な財産だと気づいたのです。

八代目当主 長谷康弘さん
康弘さんは工房や事務所として使われてきた歴史ある建物を展示室や休憩室として活用したり、遊歩道を整備して展望台を設けたりして、人を呼び込む試みを始めました。少しずつ他の窯元や地域の飲食店も賛同し、今では毎年5月の窯出し市に約3万人も訪れる観光の場となっています。

斜面を利用して築かれた16連房の登り窯は、下から上へと火が上がる原理を利用して効率良く熱を伝えていくもので、昭和40年代まで活躍。現在も国の登録有形文化財として大切に保存されています
炊飯土鍋「かまどさん」の誕生
施設の整備と並行し、康弘さんは父で先代当主の優磁(ゆうじ)さんとともに、現代の生活に沿った製品の開発にも力を入れました。美味しいご飯を手軽に炊ける土鍋ができれば必ずヒットすると信じて、来る日も来る日も試作品を作る日々が続きます。厚みや形状の違い、土の成分、釉薬(ゆうやく)のかけ方など、検討する事項は多岐にわたりました。
土鍋の炊飯が敬遠される要因のひとつ、吹きこぼれを防ぐ方法としては二重蓋(ぶた)を考案。重みのある内蓋のおかげで、悩みの種だった吹きこぼれを解消することに成功します。開発段階では、康弘さんの妻、圭未(たまみ)さんが実際に何度もキッチンで使い、忌憚(きたん)のない意見を提供したそうです。

素焼きの状態で積まれた鍋の蓋。この後釉薬をかけ、本焼きを行います
こうして、火加減いらず・吹きこぼれなしの炊飯土鍋「かまどさん」が2000年に誕生しました。著名な料理研究家が愛用しているとテレビで紹介したことから人気に火がつき、問い合わせのため電話回線がパンクしたというエピソードも。家族で力を合わせて開発した新しい商品は長谷園の窮地を救い、発売から20年を経ても予約待ちの状態が続いています。

規格品を作るのはガス式の窯ですが、小型の登り窯も年に1回は稼働。昔ながらの製法を伝承する機会を設けています

展望台に並ぶベンチやテーブルは、陶芸作家の作品。伊賀の里を見下ろしながら一息つけるとっておきの場所

鍋本体に取っ手をつける工程。双方の水分量が異なると強度に支障が生じるため、乾燥具合を見極めながら作業します
集いのためのものづくり
長谷園のものづくりの精神は、「作り手は真の使い手であれ」という言葉で表現されています。康弘さんと圭未さんは自社の製品を毎日使い、新製品のアイデアや改良のヒントを得ています。
“企画開発会議”も先代や会社の仲間とともに長谷家の食卓を囲んで行われるのだとか。土鍋で調理したバリエーション豊富な料理を食べながら、そしてお酒を飲みながら、こんな鍋があればうれしい、この製品はもっと改良できないかと、話は尽きることがありません。
美味しく料理できるだけでなく、家族で食卓を囲んで楽しめるものを作りたい、と康弘さん。「かまどさん」のほか、卓上で燻製を作れる「いぶしぎん」、食感の良い蒸し料理を味わえる「ヘルシー蒸し鍋」、炭火焼きのように食材をふっくら焼ける「ふっくらさん」など、次々とこだわりの製品を生み出しています。ひとつ世に出すまでには、年単位の時間をかけることも。長谷園の製品は土鍋の概念を超え、冬場だけでなく年中活躍する食卓のパートナーになりました。

主屋の縁側で談笑するご夫妻。康弘さんが生まれ育った築200余年の屋敷は、イベント時などに公開されています
使い手の立場で考える
使う人の視点に立つ。この思いは製品開発以外にも表れています。ある時、鍋を購入した顧客にアンケートをとると、ほとんどの人は喜んで使ってくれているものの、蓋などが壊れて使っていないという人がいると分かりました。そこで康弘さんは、パーツの販売を始めたいと考えます。パーツ販売は利益が薄く手間もかかるため、業界ではほぼ例がありません。社内でも反対の声が上がりましたが、自分がお客さんなら販売してほしいと思わないかと説得したそうです。「買ってもらうことが目的じゃない、長く愛用してもらいたいんです」
コロナ禍によって家で過ごす時間が重視され、手料理の良さが再発見されている昨今。日本各地の家庭で長谷園の愛用者が増えています。伊賀の里で始まった美味しい革命は、これからも多くの食卓に笑顔をもたらすことでしょう。

大正時代に建てられ、かつて事務所として使われていた「大正館」を休憩室として開放。自動販売機でコーヒーを買うと、オリジナルのカップをそのまま持ち帰れるサービスが大人気

「かまどさん」で炊いた絶品の白ご飯

煙が外に漏れず、気軽に燻製料理が楽しめる、「いぶしぎん」

「ふっくらさん」はタジン鍋に似た構造。食材をふっくらと焼けます

関連するコンテンツ
2021年7月現在の情報となります。


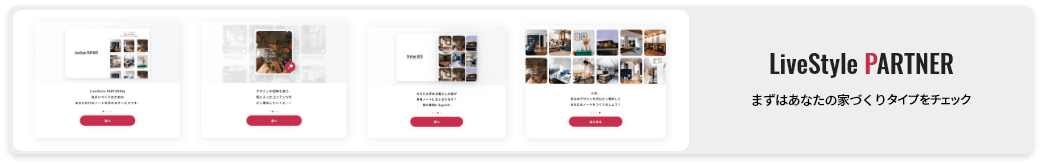


![[あなたと描くリブスタイルデザイン情報誌 and.y] and.y 冊子をお申し込みいただき、冊子内の限定プレゼント企画にぜひご応募ください!冊子を申し込む](/tryie/and/common/images/bnr/bnr_pre.jpg)

