日本の美しい伝統工芸、九谷焼の産地で新しい風を起こしている窯元があります。
連綿と続く窯の歴史の継承を担い、その可能性を追求する若き六代目、
上出惠悟さんにお話を伺いました。
産地に吹く新風
明の文人が笛を演奏する「笛吹」の絵柄と思いきや、よく見るとギター演奏やスケートボードなどに興じている。そんなポップで遊び心のある九谷焼を生み出しているのは、創業140余年の老舗窯元、上出長右衛門窯(石川県能美市)です。
九谷焼は石川県南部を中心に生産される色絵磁器。青・黄・紫・紺青・赤の五彩や金色があでやかに施されたものや、染付といってブルーのグラデーションで描かれたものがあります。もともとは加賀藩主らの注文を受けて生産された絢爛(けんらん)豪華な食器類であり、現在も多くは高級割烹食器として用いられています。シール状の絵柄を張り付けて焼成する「転写」の九谷焼もありますが、長右衛門窯では職人の手仕事にこだわり続け、一点一線、手描きで絵付けをしています。
かつては日本を代表する磁器の一つとして繁栄をきわめた九谷焼の産地ですが、他の伝統工芸と同じく、時代の流れや景気の後退によって苦難の道をたどることになります。産業そのものが衰退し、規模を縮小したり、廃業したりする窯元も現れるようになりました。
「子どもの頃から当たり前に見慣れた窯の風景が無くなってしまうのは、どうしても受け入れられなかったんです」。そう語るのは上出長右衛門窯六代目、上出惠悟さん。父である五代目から窯を受け継いだ若き担い手は、一つ一つ、しっかり言葉を選んで想いを語ってくださいました。どこかユーモラスな絵柄の食器類や、見る人を引き付けるチャーミングなフォルムのオブジェ達は、彼の人柄から生まれてくるのだと納得できるような雰囲気の持ち主です。

守りたいもののために
上出惠悟さんは1981年石川県生まれ。子どもの頃は絵を描くのが大好きで、「お茶碗屋さんかおもちゃ屋さんになることが夢」でした。県立工業高校でデザインや広告を学んだ後、東京藝術大学の絵画科油画専攻に進学。陶芸ではなく油画を選んだのは、「陶芸はいつか実家に帰ればできる」という思いがあったからでした。まずは好きなことをしようと考えて始まった大学時代は、自分の作品制作に向き合い、自身が何をすべきか模索する日々だったそうです。
時が過ぎ、その答えがはっきりしないまま3年生になった惠悟さんは、自分のルーツを探すため1年休学して実家に帰る決意をします。そこで目の当たりにしたのは、往時の勢いを無くした窯の姿でした。
「いつか」ではなく、「今」じゃないと間に合わない。長右衛門窯を守りたい、職人の手仕事を守りたいと強く感じた惠悟さんは、「この道では食べていけない。帰ってくるな」という父の反対を押し切って、卒業後すぐ故郷に戻りました。東京で多くの人に出会い、物事に触れ、さまざまな文化や情報に接してきた経験から、「できることはまだたくさん残されているはず」と確信を持っていました。

伝統柄の「笛吹」(中央)を現代的にアレンジしたシリーズ。他にも、ラジカセを担いだ笛吹、ドラムをたたく笛吹などさまざまなバージョンがあり、見ているだけでも楽しい
作家・上出惠悟の誕生
惠悟さんの出世作となったのは、卒業制作作品『甘蕉(バナナ)房色絵梅文』です。大学時代を通じて「何を表現すべきか」を追求してきた惠悟さんは、素材や技術が大前提として存在し、そこから「何を表現できるか」を考える工芸の面白さに気づきました。素材そのものと対話するうち、磁器特有の滑らかな素材感が果実のしっとりとした質感に似ていることが見えてきて、どこかひょうきんな雰囲気を醸す白いバナナを制作。この斬新なアイデアが各界で注目を集め、作家・上出惠悟の名前は広く知られるようになりました。

磁器の滑らかな質感から発想した大学の卒業制作作品 『甘蕉(バナナ)房 色絵梅文』( photo by Kenichi yamaguchi)
それからは商品開発の仕事や販売促進の仕事をする傍ら、海外企業からの依頼による作品制作や、有名ブランドやアーティストとのコラボレーション作品をつくり、華々しい活躍をすることに。しかし、「長右衛門窯ではなく上出惠悟ばかり注目される状況には、釈然としないものがありました」
そんな折、惠悟さんが敬愛するスペイン人デザイナーのハイメ・アジョン氏への熱い“直訴”が受け入れられ、コラボレーションで長右衛門窯商品の企画プロジェクトを進めることに。デザイナーが入り込みづらい伝統工芸の世界に風穴を開けるとともに、秀でた職人技をもつメーカーとして世の中に認識されるきっかけになりました。

ハイメ・アジョン氏とのコラボレーションで生まれた『醤油さし(受皿付)鳥型』。食卓にアートを添えるユニークな逸品

圧力鋳込成形によるレリーフ皿、『八寸丸皿 百果刻文』(乾燥状態)。ソースなどを入れるとみずみずしいフルーツの柄が浮かび上がります

九谷焼らしい五彩で描いた角形の銘々皿

写真右は愛らしい紙風船を模した小鉢。左はプロダクトデザイナー・小林幹也氏とのコラボで生まれたPICNICシリーズのカップ&ソーサー
会話の生まれる食器
惠悟さん自身も生活の中で長右衛門窯の商品を愛用していますが、中でも愛してやまないのが、冒頭で紹介した「笛吹」の湯呑(ゆのみ)です。「これがあったから実家に帰ってきた」ともいえるほど大切なもの。もともとは古染付の柄で、四代目の祖父の時代から描き続けてきたそうです。
「何十年も描いているうちに、だんだん髪型が変わったり表情が変わったりしているのが面白いんですよね。東京で一人暮らしをしている時もずっと手元に置いていました」。惠悟さんにとって笛吹は、いつもそばにいる懐かしい家族のような存在なのかもしれません。

手作業で寸分違わぬ型を作る手引き成形。緊張感が漂います
そんな笛吹を現代風に表現することで、若い世代の人達が面白いと感じ、手に取りたくなる湯呑が生まれました。アレンジを加えることにちょっと罪悪感をもちながらも、形を変えてもなお存在する笛吹の魅力や普遍性を再認識したそうです。
食べ物を入れたりお茶をくんだりする分には必要のない、食器の「絵柄」の意味に気づいたのは、偶然出会った出来事がきっかけでした。ある日友人と入った喫茶店でたまたま長右衛門窯の茶器が使われており、何げなく「ウチのだ」と話していると、驚くことに隣に座ったカップルも器の絵柄について会話をしていたのです。「会話の生まれる食器って、なんて素晴らしいんだろうと思いました」。現代版の笛吹も若い世代のテーブルの上で魅力を放ち、何げない会話をもたらしていることでしょう。

多くの人に伝えるために
食器やオブジェのデザイン企画から、成型、焼成、絵付け、商品の販売まで一貫して行うのが長右衛門窯の特徴です。東日本大震災後、惠悟さんの学生時代からの友人も石川県に移住し、窯の仲間として参加。彫刻科出身の友人が加わることで、長右衛門窯は石膏(せっこう)型を使った人形づくりも積極的に行うことができるようになりました。
こうした製造現場のことをもっと知ってほしいという想いから、年に1回、「上出長右衛門窯 窯まつり」として窯を開放しています※。工場見学やろくろ師への入門体験は大人にも子どもにも大人気。地元のカフェやショップも敷地内に出店して、日本各地からたくさんの人が訪れます。

一点一線、丁寧に絵柄を入れていく絵付け職人
目標に縛られず、その時その時に新鮮と感じることを追いかけたいと語る惠悟さん。伝統を背負いながら決してそれを大きな荷物とは思わず、連綿とつながる大きな流れの中で自由に泳ぎ続けることを楽しんでいるようです。先代から受け継いだものに異文化を融合させながら、これからも九谷焼の新しい魅力を創造していくことでしょう。
※「上出長右衛門窯 窯まつり」の開催時期については、http://www.choemon.com/をご確認ください。

上:素焼き状態の「ちょうえもん招猫鈴鳴り」。左手を上げているのは人(客)を招くポーズ
下:凸凹のある面にも繊細な絵柄を描けるのは、手描きの絵付けならでは
PROFILE
上出 惠悟さん(かみで けいご)
1981年石川県生まれ。合同会社上出瓷藝(かみでしげい)代表。2006年 東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。九谷焼窯元・上出長右衛門窯の六代目。窯の製品の企画やディレクションを行う一方で、作家としても活動している。


ショールーム
2020年8月現在の情報となります。


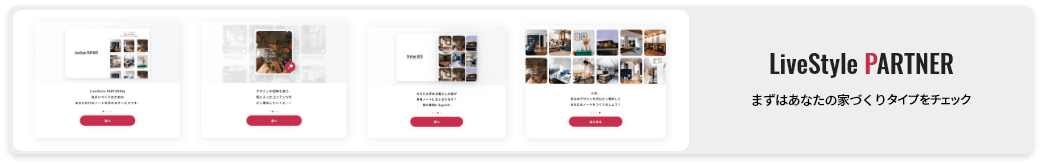


![[あなたと描くリブスタイルデザイン情報誌 and.y] and.y 冊子をお申し込みいただき、冊子内の限定プレゼント企画にぜひご応募ください!冊子を申し込む](/tryie/and/common/images/bnr/bnr_pre.jpg)

