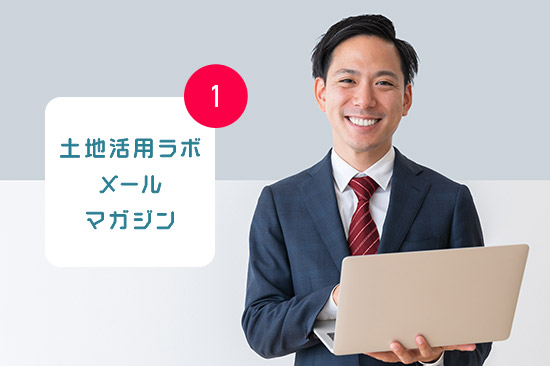コラム No.27-104
コラム No.27-104秋葉淳一のトークセッション 第3回 中小企業が生き残るために、使命として取り組む株式会社ROMS 代表取締役社長 前野 洋介 × 株式会社フレームワークス 会長 秋葉淳一
公開日:2024/12/26
自動化ソリューションで社会課題を解決し、より良いものを使える世界へ

前野:私たちも、いわゆる物流という観点で、大企業、中堅企業、中小企業を分けて見ていかないといけません。大和ハウス工業さんがお付き合いされているところは大企業と中堅企業が多いと思うので、そこは正攻法で、大企業、中堅企業に合うモデルを見出して、ご提案して、要件に合うか合わないとかを考えればいい。一方、同時進行で注力したいと思っているのは、ラストマイル的なものを含めた中小企業です。そこだけに注力するというわけではありませんが、中小企業の方々にいかにして「自動化」という仕組みを使っていただくことができるかが大事だと思っています。
現在どこの企業も人手不足が大きな課題です。大企業はネームバリューでまだ人が集まりやすいですが、中小企業では本当に厳しい状況が続いています。そして中小企業にとって人が集まらないことは死活問題です。中小企業の方々が生き残りをかけた動きをしている中で、自動化は、人手が集まらない際の代替手段となります。大企業が取り組む自動化とは、モチベーションがまったく異なる世界での話です。そのような方々に対して自動化が選択肢になるようなソリューションを提供することは、われわれがスタートアップとしてやる以上、使命、目的として捉えるべきだと思っています。
秋葉:ロボット革命・産業IoTイニシアティブ協議会(RRI)が推進している物流倉庫TC(Technical Committee)のロボットフレンドリーの取り組みは、どちらかというと大企業向けではありません。中小の会社でもロボットを導入できるような環境を構築するためにさまざまなことを考えています。集まっているのは大企業ですが、皆会費を払って、ボランティアで議論をしています。実証実験を行い、標準化のためのガイドラインを作って、「天面の強度をこうしないと把持が100%にならないから費用対効果が上がらない」など、問題をひとつずつ潰していっています。前野さんがおっしゃるように、最終的にさまざまな現場で動いているのは多くの中小企業です。ここが破綻すると、小売も物流もすべて日本のインフラが崩れてしまいます。そこを何とかするという思いが大事で、格好いいことだけではなく、そこもやっていかなければいけないと思いますね。
前野:そう思います。時間がかかるけど規模が大きい大企業と、即断即決してくれるけれども予算が少ない中小企業。そこのバランスを取りながらやっていく必要があるのは間違いないのですが、せっかくやるのであれば、社会的課題も解決しつつ、大企業か中小企業かは関係なく全般的により良いものが使える世界を作っていくことを考えたいと思っています。あえて大企業から来ているメンバーもいるので、そういうところに面白さや意義を感じてくれているメンバーが多いのも事実です。
秋葉:フィジカルな領域なので中小企業が止まると破綻しますからね。クラウド上のソフトウェアで動かしているだけの世界ではありません。国のガイドラインを見て、うちには無理だと言っている中小の会社の方々にこそ、ROMSの製品のようなソリューションをアピールしたいですね。
前野:私は弊社の製品が合わない会社には合わないとはっきり言います。いわゆる競合と言われている会社の製品であっても、そっちの方が良かった場合は、「今回は当社のものは要件不適合です。こちらの会社のこの製品のほうが合うので、よかったらご紹介しますよ」と率直に言っています。自動化は使っていただく方に末永く使い倒していただくことが一番大事で、無理して入れると「導入したけど結局使えなかった」と言われてしまい、結局、自分たちに跳ね返ってくるだけです。
当社でさまざまなラインナップを用意している理由もそこにあります。最後には他社の紹介もしたほうがいいという考えでやっています。
秋葉:本来の目的は、物流センター全体のパフォーマンスを上げることです。ところが多くのお客様はその中のひとつを切り取って、「保管効率を上げたい」など一部の課題を取り上げます。保管効率を上げるだけが目的ではないはずなのに、その要件に対してだけの議論をしがちです。なぜ上げたいのかを考えると、もしかするとROMSのほうがいいかもしれないし、ROMSではないほうがいいかもしれない。そこは私たちも含めて提供する側がお客様の商売や事業を理解して、きちんとそういう会話をしていかなければいけませんね。
前野:社内では生産技術の重要性についてよく話をします。全工程を考えたうえで最適なものは何か考えるべきだということです。残念ながら物流の世界ではその生産技術の考え方がまだ浸透していませんが、いわゆる製造、FA(Factory Automation)の世界では生産技術が当たり前です。
秋葉:多分私たちが製造出身だからですね。
前野:秋葉さんは製造出身で、その考え方が所与の前提になっているのだと思います。物流にはそれがまだ少ないので、点だけで「こうしたい」と考えて、「それをしたらこの後どうするか」がほとんどありません。これは仕方のないことです。物流の会社は中小であればあるほど社長がすべてを行っています。アルバイトスタッフが休んだ場合は社長自ら荷下ろしをしたりします。そういったところも含めて、私たちは生産技術の観点から本当はどこが問題なのか話します。「そもそもWMS(Warehouse Management System:倉庫管理システム)を使いこなしていますか」といった話になることもあります。物流はそこからやっていく必要がある世界だと思っています。
リアルのものづくりで作り手のDNAを取り戻す

秋葉:国際物流総合展の大和ハウス工業のブースに、ROMSの「Nano-Sorter」を出展していただきました。Nano-Sorterは、バーコードを読ませていくと、例えば、ある棚にすごいスピードで商品を振り分けて、指示を出すとその商品がまとまって出てきて、ひとつの箱に詰めて出荷します。これも面白いですね。ここでまたピボットの可能性もあります。例えば、その箱を株式会社LexxPlussの製品がけん引するカゴ車(※)に入れると、トラックバース近くまで引っ張っていくようなイメージです。
※:かご台車や汎用台車を500kgまで自動搬送する製品
前野:それもありで、既に計画に入れています。
秋葉:これまでは、物流の人たちは指示されたことをきちんとやるのが仕事でした。考えることは、メーカーや卸、小売業、あるいは委託先のエンジニアがやればよかった。ところが今、それではだめだとなってきたわけです。物流の人たちが考えなければいけなくなってきたというのが今の状況です。物流の人たちがすべて理解しているとは言えない状況の中で、ベンダーは、自社製品を次々と提供してきます。そこを、物流に関わるエンジニアを抱えている私たちのような企業が間を取り持ち、本質的な目的や物流効率化に向けてどのようにお手伝いしていくかが重要だと思っています。
前野:いわゆるベンダーロックイン(システムの保守や改修を特定のベンダーに依存し、他のベンダーへの乗り換えが困難になること)の状態となっているところがありますよね。
秋葉:そこにROMSやHacobuのような会社が出てきたわけです。ソフトウェアのエンジニアも、作業指示を中心にしたWMSから、倉庫全体の効率化をするようなWMSやWES(Warehouse Execution System:倉庫運用管理システム)を提供するところまできました。やはり変わってきているのではないでしょうか。ROMSが参入して1年ですが、その前の10年も業界として変わってきたと言われていました。それがここにきて変わり方がとんでもなく大きくなっています。
前野:一番大きいのは、少子高齢化で人口が減ることが分かりきっていることです。さらに2024年問題で労働力の確保が相当厳しくなっています。働ける人、働く時間の総量が決まってしまったことが、自動化やソフトウェアの導入などデジタル化が一気に進んでいる大きな要因のひとつだと思います。2000年代初頭と2010年代は、いろいろな課題があったにせよ、まだ人という労働力がありましたし、その方々に頑張ってもらっていました。日本人の労働力はとても生産効率が高いうえに時給も安いので、それでどうにかできていました。今それができなくなり始めているのが目に見えているので、皆が自動化、デジタル化を見始めたのだと思います。
秋葉:そういう局面であるのは間違いないですね。
前野:この流れは私たちが、自分たちで作っていることにも影響しています。やはり作って提供することにこだわるべきです。日本にはメーカーがたくさんあるのに、なぜ作らないのか疑問です。ものを作らないメーカーに優秀なエンジニアが行こうと思うでしょうか。皆自分で自分の首を絞めています。作らなくなって、企画という名のもとデスクワークだけをさせる。そんなことはエンジニアがやりたいことではありません。作りたいという思いがあって、作って、作ったものを実際に使ってもらって、改善して、イノベーションを起こすことは、本来人間が持っているはずのDNAだと私は思っています。それを取り上げているのです。
作れる、作る、使ってもらう、どんどん変えていくということをやらないと、メーカーとして中身が何もない状態になってしまいます。特に日本はそうなり得ると危惧しています。だからこそ自分たちで作ったほうがいいと思うのです。作ったことがない人は、それがどうやって使われるのか、どうやったら良くなるかも絶対に分からないでしょう。これは日本のメーカー全体で言えることなのではないでしょうか。
大和ハウス工業さんも建物というリアルのものを作っていますが、リアルのものを作る方々は、その価値を理解し、そこで品質を追求しています。世の中はリアルのものがないと何も成り立ちません。だからハードウェアを作るのです。ソフトウェアはハードウェアの上にさらなる付加価値を提供しているもので、土台としてのハードウェア、リアルのものにどう磨きをかけるかは常に考えていかないといけません。これからさらに追求していきたいです。
もうひとつ、マテハン業界で危惧していることは、最初にお話しした海外製が多いことです。海外製の品質が悪いわけではありません。ただ、受け入れているだけだと、作ったり、それを良くしたり、改良しようとした時に、思うように出来ません。
秋葉:間違いないですね。思ってから何十年とかかりますよ。自分たちで作れなくなった時点でメーカーとしての目的が果たせなくなります。
前野:1回なくした瞬間にできなくなります。自動化の流れによって完全にその方向に向かっているので、そこに対して一石を投じるべきではないでしょうか。GDPが今や4位になっても、もともとは2位だった大きなマーケットの日本で自動化は必然です。なぜやらないのでしょうか。代理店ビジネスのようなことをしても構いませんが、日本を代表するような企業が、海外メーカーの製品を持ってくることが、私にはまったく理解できません。これは自戒の念を込めて言っていることです。ハードウェアを作ったこともなければエンジニアでもない文系出身の私でもこうして社長としてハードウェアの会社やっていますよと、警鐘も含めてアピールしていきたいと、自分のアジェンダとして思っています。
ROMSの未来戦略

秋葉:ここまで物流系の話がほとんどでしたが、今後の予定は何かありますか。
前野:当然、物流をメインの領域として見ていますが、実は製造系、ファクトリーオートメーションの話も結構きているのです。ただ、製造ラインに一足飛びに飛ぶつもりはないので、ファクトリーオートメーションの中の格納や搬送、在庫など、そちら側はきちんと見ていこうと思っています。
秋葉:物流目線から見ると、最終の製造工程のところしか見えていないのですが、途中には仕掛かり在庫や部品、工具などいろいろなものがあります。ですから、ROMSが活躍する場は多いと思います。そこもまた小型が良かったりしますよね。
前野:製造現場は基本的に製造に場所を使いたいので、保管には場所を使いたくないです。そうすると小型かつ高さを使ったものになるので、われわれと親和性が高いのです。製造系も物流系もしっかり見て、両輪でやっていきたいですね。
今後の展望としては、開発して新しいものを生み出すこと自体が会社の価値だと思っているので、今回Nano-Streamを世に出しますが、実は次のもの、その次のものも考えていて、着手しています。ひとつ大きなアジェンダとして挙げているのは冷凍対応で、すでに着手し始めています。いろいろな方々からご要望をいただいているので、さっさと作って導入していきましょうと話しているところです。冷凍対応以外には、いくつか違うモデルを考えているので、その辺を順次やっていこうと思っています。
秋葉:先ほど私はモジュールという言い方をしましたが、やはり確固たる技術の集合体だからこそスピード感を持ってできるのでしょうね。
前野:確かに、われわれのような自動化をしているスタートアップの会社は、だいたい1領域1コンポーネントのパターンが多いです。われわれはそうではなく、いろいろなコンポーネントを集合体で作っているので、それをばらして違う形で組み合わせることができるのも強みです。シャトルも持っていますし、クレーンも持っています。コンベヤは自分たちで設計していますし、AGV(Automatic Guided Vehicle:無人搬送車)もやっています。クレーンを違うものにしたり、AGVとシャトルを組み合わせたり、それぞれの組み合わせをして、Nano-Streamとは違うモデルを作ることができます。われわれが要素技術を確立させているからこそこのような芸当ができるわけで、他ではできないやり方だと思います。
秋葉:あとはシミュレーターですね。

前野:はい、裏にシミュレーターを持っています。WCS(Warehouse Control System)やPLC(Programmable Logic Controller)のプログラムをその中に組み込んでいるので、お客様のレイアウト変更や機器構成を事前にシミュレーションできるようにし、且つそのシミュレーター上で変更箇所のコードが自動生成され、そのまま導入する実機に使えるというやり方をしています。事前にシミュレートしているので、導入して立ち上げる時にはソフトウェアのバグが出ないようになっています。
秋葉:実際の稼働までの時間が確実に短くなりますね。機器を置いてお金を稼げない期間が何カ月もあるのは本当にもったいない話です。床代は安くないですよ。
前野:シミュレーターによるコード生成とかは大手企業ではやらせてもらえません。ただし大手企業がやらない理由があります。昔から使っているWCSやPLC等のコードがあって、それを変えてしまうと、他のところの動作保証ができなくなってしまうのです。それでやらないのも分かります。ただ、そうすると「これで入れてください」というユニット売りになってしまうので、新しい価値を生めなくなってしまいます。
秋葉:結局その分の時間とお金をお客様に求めているわけです。「何のためにやっているの?」というところがずれていってしまいます。お客様からすれば選択肢が増えて、すごく良いことだと思います。ROMSの登場は、物流業界において、大きな起爆剤になりそうです。これからもスピード感ある開発を待っています。本日はありがとうございました。